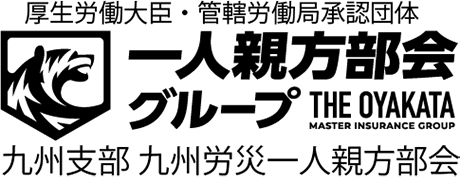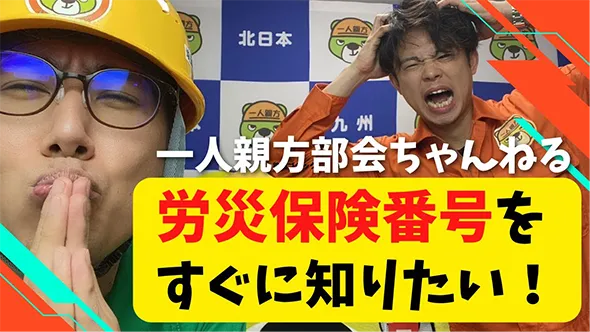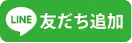1. 忘れがちな経費と知らないと損する節税テクニック
確定申告を怠ると追徴課税のリスクがある一方、正しく処理すれば大きな節税効果が期待できます。特に建設業の一人親方ならではのポイントを整理しました。
- 作業用品:作業着・安全靴などは全額経費にできます。
- 自宅兼事務所:面積割合に応じて家賃・光熱費の一部を計上可能。
- 青色申告特別控除:複式簿記+e-Taxで最大65万円控除。節税効果は大。
- 工具・機械:10万円未満は即時経費、30万円未満は特例で全額計上可能。
- 社会保険料:国民健康保険や国民年金、小規模企業共済、iDeCoは全額控除。
- 車両費:燃料費・修理費・車検代は走行記録を残せば経費として認められやすい。
2. 【専門家監修】一人親方の確定申告ミス TOP5と対策
税理士調査によると、一人親方の約70%が申告でミスを経験。特に建設業ならではの落とし穴があります。
- ミス1:「事業所得」と「給与所得」を混同。
対策:契約書を明確にし、判断に迷う場合は税理士相談。 - ミス2:経費範囲の誤り。自宅兼事務所や工具の処理で間違いやすい。
対策:事業専用口座を作り、領収書にメモを残す。 - ミス3:青色申告特別控除を使わない。
対策:事前に承認申請を提出し、複式簿記+会計ソフトで管理。 - ミス4:源泉徴収・消費税対応の不備。
対策:契約書で確認し、売上が1,000万円に近づいたら早めに税理士へ。 - ミス5:専従者給与・保険料控除の処理ミス。
対策:届出書や支払証明書を必ず保管し、制度を正しく理解。
日々の領収書管理とデジタル化が最大の防御策。税制改正が頻繁にあるため、定期的な勉強や専門家相談が安心です。
3. 一人親方の所得税が激減!? 活用すべき控除と特例まとめ
控除や特例を知らないだけで大きな損につながります。2025年確定申告で押さえておくべき制度を整理しました。
- 青色申告特別控除:最大65万円控除。電子帳簿保存とe-Taxでフル活用。
- 小規模企業共済:掛金全額控除+将来の退職金制度としても活用可能。
- iDeCo:掛金全額控除+運用益非課税。老後資金形成と節税を同時に実現。
- 工事進行基準:長期工事の場合、収入計上を分散して税負担を平準化。
- 医療費控除:10万円超または所得の5%超の医療費は控除対象。
- 扶養控除・配偶者控除:家族構成に応じた控除でさらに節税可能。
正確な記帳と領収書保管が大前提。クラウド会計ソフトや税理士との連携を活用し、自分の状況に最適な申告戦略を立てましょう。
まとめ — 確定申告は「納税」だけでなく「経営改善」のチャンス
確定申告は単なる税金の計算ではなく、自分の事業を見直す機会でもあります。売上と経費のバランスを分析し、来期の事業計画につなげることができます。
九州の一人親方の皆さんも、2025年は「正しく申告し、しっかり節税」することで、安心と成長につなげてください。