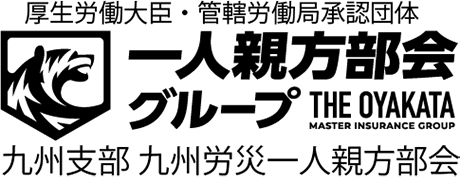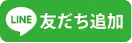工事保険について
工事保険のトラブル防止策

建設現場でのトラブルは、一瞬の判断ミスや予期せぬ事態によって発生し、多大な損失につながることがあります。「まさか自分の現場では起きない」と思っていても、実際には多くの建設会社が様々なクレームに直面しています。九州で事業を展開される建設業の経営者や責任者の皆様、工事保険の活用は万が一の事態に備える重要な経営戦略の一つです。本記事では、実際に発生した工事中のクレーム事例を分析し、どのような保険対応がなされたのか、また、トラブルを未然に防ぐためにはどのような対策が効果的なのかを詳しく解説します。建設業界での長年の経験と保険実務のノウハウを活かし、現場で即実践できる具体的な対策法をご紹介します。工事の安全管理と適切な保険選びで、御社のビジネスを守りましょう。
1. 【工事中のトラブル】実際のクレーム事例から解説!建設業必見の保険活用術
建設現場でのトラブルは一度発生すると高額な賠償責任を負うケースが少なくありません。実際に起きたクレーム事例を見ていくことで、工事保険の重要性と適切な対応策が見えてきます。
ある中規模建設会社では、マンション改修工事中に足場が崩れ、隣接する店舗の看板を破損させるという事故が発生しました。損害額は150万円に上りましたが、工事保険(請負業者賠償責任保険)に加入していたため、保険会社による示談交渉と賠償金の支払いがスムーズに行われました。
また、住宅建設現場での事例では、強風により資材が飛散し、駐車中の車両5台に傷をつけるという事故が発生。総額200万円の損害賠償となりましたが、建設工事保険のカバー範囲内だったため、建設会社の経営に大きな影響を与えることなく解決しています。
しかし、保険に加入していても注意が必要です。東京都内の大和建設では、工事保険に加入していたものの、契約内容の確認不足から、地下配管工事中の水漏れ事故による近隣住宅の浸水被害が補償対象外となり、自社負担で3000万円の賠償金を支払うことになった事例もあります。
適切な工事保険選びのポイントは以下の3点です:
1. 工事内容に合った補償範囲を確認する(第三者賠償、工事対象物、使用機械など)
2. 支払限度額が十分か検討する(特に都市部や高額な施設近隣での工事)
3. 免責事項を細かくチェックし、必要に応じてオプション追加を検討する
保険代理店のMS&ADインシュアランスでは「建設業は業種特有のリスクがあるため、一般的な賠償責任保険だけでなく、工事特有の保険商品を組み合わせることが重要」と指摘しています。
トラブル発生時の初動対応も重要です。事故発生時は、①現場の安全確保と被害拡大防止、②速やかな保険会社への報告、③証拠写真の撮影と状況記録が鉄則となります。これらの対応が迅速かつ適切に行われれば、保険金支払いもスムーズになります。
工事保険は単なるコストではなく、事業継続のための重要な投資です。実際のクレーム事例から学び、自社の工事内容に合った保険選びを行うことが、建設業のリスクマネジメントの第一歩となるでしょう。
2. 建設現場の「ヒヤリハット」を防ぐ!工事保険クレーム事例と効果的な対策法
建設現場では日々さまざまな「ヒヤリハット」が発生しています。これらの小さな事故や危険な状況が、重大な災害や工事保険のクレームにつながることも少なくありません。実際の工事保険クレーム事例を分析すると、多くの事故は事前に防げた可能性があります。
まず注目すべきは「足場からの転落事故」です。ある高層マンション建設現場では、作業員が安全帯を正しく装着していなかったことが原因で転落事故が発生。このケースでは、日常的な安全帯の点検と正しい使用方法の定期的な教育が実施されていれば防げた可能性が高いでした。
次に多いのが「資材の落下による第三者被害」です。東京都内の建設現場では、強風により固定が不十分だった資材が飛ばされ、隣接する商業施設の窓ガラスを破損させる事故が発生しました。この事例からは、気象情報の確認と資材の確実な固定の重要性が学べます。
また「重機による事故」も看過できません。三井住友海上の調査によると、建設機械の操作ミスによる事故は全体の約20%を占めるとされています。特に視界不良による事故が多く、監視員の配置や死角をなくす工夫が効果的です。
さらに「地下埋設物の損傷」も多発しています。東京ガスや関西電力などの地下埋設管を誤って損傷させるケースでは、工事前の詳細な現地調査と関係機関との密な連絡体制が不可欠です。
これらの事例から効果的な対策をまとめると:
1. 定期的な安全教育と現場チェックの徹底
2. 天候変化に応じた作業計画の見直し
3. KY(危険予知)活動の日常化
4. 作業前ミーティングでの注意点共有
5. ヒヤリハット情報の収集と分析
特に注目すべきは、損害保険ジャパンや東京海上日動が提供している「事故防止コンサルティング」です。これらのサービスを活用することで、専門家の目線から現場のリスクを洗い出すことができます。
また、工事保険の補償範囲を正確に理解しておくことも重要です。例えば、建設工事保険は自然災害による損害をカバーしますが、請負業者賠償責任保険は第三者への賠償責任をカバーするというように、目的に応じた保険選びが必要です。
ヒヤリハットの段階で対策を講じることは、大きな事故を未然に防ぐだけでなく、工事の円滑な進行や保険料の上昇防止にもつながります。日々の小さな安全対策の積み重ねが、最終的には大きなコスト削減と信頼獲得につながるのです。
3. 工事保険が適用されなかった実例から学ぶ!プロが教える確実なリスク対策とは
工事保険が適用されなかったケースは実務現場で珍しくありません。ある土木建設会社では、地下埋設物を誤って破損させる事故が発生しましたが、事前の地下埋設物調査が不十分だったとして保険金が支払われませんでした。このように「当然カバーされると思っていた」事例でも実際は補償対象外となるケースが多発しています。
まず注意すべきは「免責事由の正確な理解」です。多くの工事保険では、設計ミスや施工不良に起因する損害、経年劣化による損害などは免責となります。東京海上日動火災保険の約款では、「保険の対象の施工、材質または製作の欠陥」による損害は補償されないと明記されています。
次に重要なのが「告知義務の徹底」です。ある建設現場では、地盤の状態について正確な情報を保険会社に伝えていなかったため、発生した地盤沈下による損害が補償されませんでした。損保ジャパンの担当者によると「契約時のリスク状況を正確に伝えることが極めて重要」とのことです。
また「適切な保険金額の設定」も重要です。実際の工事価額より低い保険金額で契約していた場合、比例てん補の原則により、保険金が減額されるケースがあります。三井住友海上の調査によれば、約35%の契約で保険金額が適正に設定されていないという結果が出ています。
最も確実なリスク対策は「専門家との協働」です。保険ブローカーや専門の代理店と連携し、工事の特性に合わせた保険設計を行うことで、補償の抜け漏れを防止できます。あいおいニッセイ同和損保では、施工業者向けに保険内容の事前確認サービスを提供しており、工事開始前のリスク評価を無料で実施しています。
また「事故発生時の初動対応マニュアル」の整備も不可欠です。事故発生から24時間以内に保険会社への報告が必要なケースが多く、報告遅延が保険金支払いの障害となることがあります。具体的には、現場の写真撮影、関係者への聞き取り、損害状況の記録など、証拠保全の手順を明確にしておくことが重要です。
プロが実践する「リスク移転戦略」としては、主契約の工事保険に加えて、第三者賠償責任保険や建設工事保険特約など、複数の保険を組み合わせることで補償の網を広げる方法があります。これにより、一つの保険で補償されなかった場合でも、別の保険でカバーできる可能性が高まります。
工事保険が適用されないリスクを最小化するためには、これらの対策を総合的に実施することが必要です。適切な保険選びと契約内容の理解が、将来の思わぬトラブルから事業を守る鍵となるでしょう。
投稿者プロフィール
- 九州労災の中の人。
一人親方様の支援を仕事としています。
最新の投稿
 一人親方豆知識2026年2月4日一人親方のための確定申告完全ガイド!九州の税理士が教える役立つ情報
一人親方豆知識2026年2月4日一人親方のための確定申告完全ガイド!九州の税理士が教える役立つ情報 未分類2026年1月20日【建設業必見】工事保険の選び方と最新トレンド2026
未分類2026年1月20日【建設業必見】工事保険の選び方と最新トレンド2026 未分類2026年1月22日【2025年最新】一人親方の税金対策で年間30万円を取り戻す方法
未分類2026年1月22日【2025年最新】一人親方の税金対策で年間30万円を取り戻す方法 一人親方豆知識2026年1月21日九州を拠点に活躍する一人親方が教える経営の極意と役立つ情報
一人親方豆知識2026年1月21日九州を拠点に活躍する一人親方が教える経営の極意と役立つ情報
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。
新着情報
- 2025年12月30日
- 2025年12月29日
- 2025年12月25日
元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。
お申し込みはコチラご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。

YouTubeチャンネルのご紹介
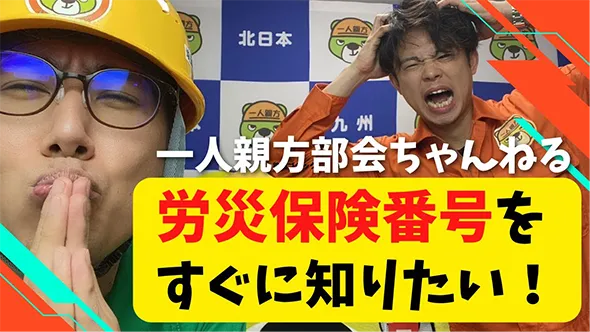
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
会員証発行までの流れ
通常3営業日以内に労災特別加入の会員証を発行(お急ぎ対応可。ご相談ください。)

- Step1必要情報をお申し込みフォームに入力送信ボタンをクリック
- Step2クレジットカードの登録画面で利用するカード情報を入力。
※現金申込みの場合、下記へお振込みをお願いいたします。
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
- Step3通常3営業日以内に労災加入の会員証を発行
- Step1左上のアイコンをクリックしてダウンロ―ド
- Step2申し込み書に必要事項を記入し、下記の番後にFAXまたは所在地に郵送
- FAX048-812-8472
- 所在地≪本部≫〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14A&M HANABATA301号
≪岩槻事務センター≫ 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
- Step3保険料支払い
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
団体概要
名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。