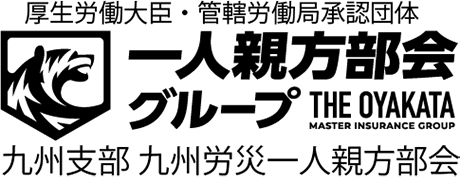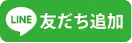工事保険について
必見!個人事業主でも安心の工事保険入門

建設業や各種工事業で個人事業主として活躍されている職人の皆様、工事中の思わぬアクシデントに備えていますか?ちょっとした不注意や予期せぬトラブルが大きな損害につながることも珍しくありません。
特に個人事業主の場合、万が一の事故やトラブルが経営の危機に直結することも。「保険は大手企業だけのもの」と思っていませんか?実は個人事業主だからこそ、適切な工事保険への加入が重要なのです。
九州を中心に活動されている職人さんたちから、「どんな保険に入るべき?」「保険料は経費になるの?」「施主との信頼関係を高める保険活用法は?」といった相談が多く寄せられています。
この記事では、個人事業主の職人さんが知っておくべき工事保険の基礎知識から、税務上のメリット、そして受注につながる保険の活用方法まで、わかりやすく解説します。自分の技術と経営を守るための工事保険、ぜひ最後までご覧ください。
1. 【工事リスク対策】個人事業主の職人さんが知っておくべき工事保険の基礎知識
個人事業主として建設・工事の仕事をしている職人さんにとって、工事中の事故や損害は大きな経済的負担となります。一つのミスが事業継続を脅かすこともあるため、適切な工事保険への加入は必須と言えるでしょう。
工事保険とは、建設工事中に発生する様々なリスクをカバーする保険です。主に「請負業者賠償責任保険」と「建設工事保険」の2種類があります。請負業者賠償責任保険は工事中に第三者に与えた損害を補償し、建設工事保険は工事対象物自体の損害を補償します。
例えば、大工として住宅のリフォーム工事中に誤って隣家の窓ガラスを割ってしまった場合、請負業者賠償責任保険が適用されます。一方、台風で工事中の建物が損害を受けた場合は建設工事保険でカバーされます。
個人事業主の場合、保険料は経費として計上できるため税務上のメリットもあります。保険料は工事の規模や内容、補償範囲によって異なりますが、月々数千円から加入できるプランも多く提供されています。
大手の損害保険会社では、個人事業主向けのパッケージプランを用意しています。例えば、東京海上日動火災保険の「請負業者賠償責任保険」や、三井住友海上の「ビジネスオーナーズ」などがあります。加入前に複数の保険会社から見積もりを取り、自分の業務内容に最適な保険を選ぶことをおすすめします。
工事保険を選ぶ際のポイントは、①自分の業種に必要な補償内容か、②補償金額は十分か、③免責金額(自己負担額)はいくらか、④特約条項は必要か、を確認することです。特に大型工事の場合は、発注者から特定の補償内容を求められることもあるため、契約内容をよく確認しましょう。
適切な工事保険に加入することで、万が一の事故や災害が発生しても事業を継続できる安心感が得られます。個人事業主こそ、自分の仕事と生活を守るための「備え」として、工事保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
2. 【保険料は経費になる?】個人事業主の職人さんのための工事保険完全ガイド
個人事業主として建設業や工事業を営む職人さんにとって、工事保険の保険料は重要な支出の一つです。結論から言うと、工事保険の保険料は「必要経費」として計上できます。これは確定申告の際、事業所得から差し引くことができる項目として認められています。
例えば、年間50万円の工事保険料を支払った場合、その全額を経費として計上でき、課税対象となる所得を減らすことが可能です。ただし、プライベートでの使用が混在する車両保険などと違い、工事保険は事業目的が明確なため、経費計上の際のトラブルは少ないでしょう。
個人事業主の職人さんが検討すべき主な工事保険には以下のものがあります:
1. 請負業者賠償責任保険:作業中に第三者に与えた人身・物的損害をカバー
2. 建設工事保険:工事中の資材や仮設物の損害に対応
3. 労災上乗せ保険:従業員や一人親方のケガや疾病に対する補償を手厚くする
特に注目したいのは、一人親方の場合の労災保険の扱いです。政府労災に特別加入しつつ、さらに上乗せ保険に加入することで、万が一の際の補償を充実させることができます。
保険料の節約方法としては、複数の保険をパッケージ化した「建設業総合保険」などの活用がおすすめです。東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社では、個人事業主向けのパッケージプランを提供しています。
また、見積りを取る際のポイントとして、「過去の事故歴」「年間工事高」「作業内容の詳細」を正確に伝えることが重要です。特に高所作業や解体工事など、リスクの高い作業を行う場合は、その旨を伝えておくことで、後々のトラブルを避けられます。
経費計上の際には、保険の契約書や領収書をきちんと保管しておくことが大切です。デジタル化して管理する方法も効率的で、クラウド会計ソフトと連携させれば、確定申告の手間も大幅に削減できるでしょう。
工事保険は単なる出費ではなく、事業を守るための投資であり、同時に税制上のメリットも享受できる賢い選択です。職種や工事内容に合わせた最適な保険選びで、安心して仕事に取り組める環境を整えましょう。
3. 【施主からの信頼UP】個人の職人さんが工事保険に加入するメリットと選び方
個人で活動する職人さんが工事保険に加入することは、単なるリスク対策以上の価値があります。特に施主との信頼関係構築において大きな武器となるのです。実際、ある東京都内で活動する個人大工の山田さん(仮名)は「保険加入を伝えたことで、高額な改装工事を受注できた」と語ります。では具体的にどのようなメリットがあり、どう選べばよいのでしょうか。
まず最大のメリットは「万が一の安心」を提供できること。工事中の事故で第三者に損害を与えた場合や、施工ミスによる補修費用などをカバーできます。特に住宅リフォームなどでは、家財や既存建物への影響も考慮が必要で、保険でバックアップされていることは施主にとって大きな安心材料になります。
次に「プロフェッショナルとしての信頼性向上」があります。三井住友海上や東京海上日動などの有名保険会社の工事保険に加入していることを名刺やチラシに記載するだけで、仕事に対する姿勢や責任感が伝わります。特に初めての施主との取引では、この信頼の証が受注率向上につながるケースが多いのです。
保険選びのポイントとしては、まず「補償範囲」の確認が重要です。自分の業種特有のリスクをカバーするものを選びましょう。例えば電気工事であれば漏電による火災リスク、水道工事であれば水漏れリスクなど、業種によって必要な補償は異なります。
また「保険金額と免責金額」のバランスも大切です。高額な保険金額設定は魅力的ですが、その分保険料も上がります。自分の工事規模に合った適切な保険金額を設定し、免責金額(自己負担額)で調整するのが賢明です。ある程度の小額損害は自己負担でカバーし、大きな損害時に保険を使う設計が経済的です。
さらに「特約の活用」も検討すべきポイント。基本の賠償責任保険に加えて、「請負業者特約」や「生産物特約」など、自分の仕事の実態に合った特約を付けることで、より手厚い保護が得られます。日本興亜損保の調査によると、適切な特約付帯により約40%の職人さんが実際のトラブル時に保険の恩恵を受けているというデータもあります。
保険会社選びでは、大手損保各社(損保ジャパン、あいおいニッセイ同和損保など)の商品を比較するのはもちろん、建設業や各種職人向けに特化した共済や組合の保険も視野に入れるべきです。例えば全建連の「まもり共済」など、業界団体ならではの保険商品は掛け金の面でメリットがあることも。
最後に、保険加入は「コスト」ではなく「投資」として考えましょう。年間数万円の保険料は、一見負担に感じるかもしれませんが、一度の事故対応でその何倍もの価値になります。また、施主への提案時に「保険完備」をアピールすることで、同業他社との差別化となり、結果的に受注増や適正価格での契約につながる可能性が高まります。
信頼される職人であり続けるために、保険は強力な味方になるのです。自分の仕事と将来を守るため、今一度工事保険について検討してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
- 九州労災の中の人。
一人親方様の支援を仕事としています。
最新の投稿
 一人親方豆知識2026年1月14日九州の気候に合わせた建築術!一人親方が伝える地域特有の役立つノウハウ
一人親方豆知識2026年1月14日九州の気候に合わせた建築術!一人親方が伝える地域特有の役立つノウハウ 未分類2026年1月15日青色申告のメリット・デメリット|一人親方の税金戦略を解説
未分類2026年1月15日青色申告のメリット・デメリット|一人親方の税金戦略を解説 一人親方豆知識2026年1月16日九州の一人親方必見!仕事を10倍効率化する現場の裏ワザと豆知識集
一人親方豆知識2026年1月16日九州の一人親方必見!仕事を10倍効率化する現場の裏ワザと豆知識集 一人親方豆知識2026年1月12日独立10年の九州一人親方が語る!失敗から学んだ成功への道と役立つ情報
一人親方豆知識2026年1月12日独立10年の九州一人親方が語る!失敗から学んだ成功への道と役立つ情報
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。
新着情報
- 2025年12月30日
- 2025年12月29日
- 2025年12月25日
元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。
お申し込みはコチラご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。

YouTubeチャンネルのご紹介
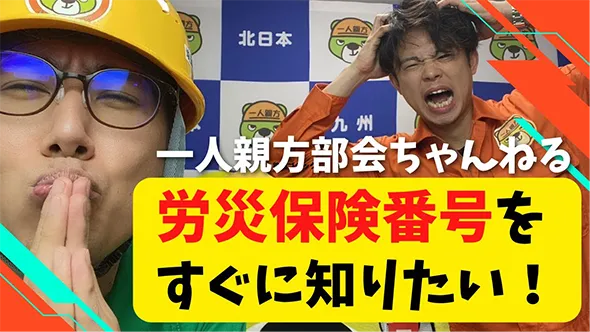
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
会員証発行までの流れ
通常3営業日以内に労災特別加入の会員証を発行(お急ぎ対応可。ご相談ください。)

- Step1必要情報をお申し込みフォームに入力送信ボタンをクリック
- Step2クレジットカードの登録画面で利用するカード情報を入力。
※現金申込みの場合、下記へお振込みをお願いいたします。
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
- Step3通常3営業日以内に労災加入の会員証を発行
- Step1左上のアイコンをクリックしてダウンロ―ド
- Step2申し込み書に必要事項を記入し、下記の番後にFAXまたは所在地に郵送
- FAX048-812-8472
- 所在地≪本部≫〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14A&M HANABATA301号
≪岩槻事務センター≫ 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
- Step3保険料支払い
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
団体概要
名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。