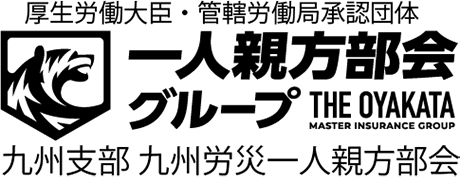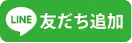新着情報
九州の一人親方が教える防災知識

近年、日本各地で大規模な自然災害が頻発しています。特に九州地方では、熊本地震や九州豪雨など、甚大な被害をもたらす災害が相次いでいます。「家族の安全を守りたい」という願いは、住宅を建てる上で最も重要な要素ではないでしょうか。
私は九州で長年建築に携わってきた一人親方として、数々の災害現場を目の当たりにし、また復興の現場で働いてきました。その経験から、「本当に災害に強い家とは何か」を日々考え、実践してきました。
この記事では、台風や地震に負けない家づくりの鉄則、熊本地震から学んだ耐震住宅の具体的な設計ポイント、そして災害時に「避難せずに済む家」を建てるための秘訣を、現場の知恵としてお伝えします。
ハウスメーカーのカタログには載っていない、実際の災害を経験した職人だからこそ知っている家づくりの防災知識。これから家を建てる方はもちろん、既存の住宅にお住まいの方にも役立つ情報をご紹介します。家族の命と財産を守る住まいづくりのヒントになれば幸いです。
1. 【台風・地震に負けない】九州の建築のプロが教える「災害に強い家づくり」3つの鉄則
九州では頻発する台風や地震から家族を守るための「災害に強い家づくり」が重要視されています。特に近年の異常気象による大型台風や予測不能な地震に対応するには、建築段階からの備えが不可欠です。地元九州で30年以上の経験を持つ一人親方として、多くの災害を目の当たりにしてきた経験から、本当に役立つ「災害に強い家づくり」の3つの鉄則をお伝えします。
鉄則その1:基礎工事に妥協しない
家の強度を決める最も重要な要素は基礎です。地震の際、建物全体を支える基礎が弱ければ、どんなに上部構造が頑丈でも意味がありません。特に九州の一部地域に見られる軟弱地盤では、地盤調査を徹底し、必要に応じて地盤改良や杭基礎の採用を検討すべきです。西松建設などの大手建設会社でも採用している鉄筋コンクリート造の基礎に、配筋を通常より増やす「ベタ基礎」は、地震の揺れを分散させる効果があります。
鉄則その2:風圧に耐える外装材と屋根の選択
九州を襲う台風の最大の脅威は強風です。時速200kmを超える風でも剥がれない外壁材と屋根材の選択が重要です。具体的には、窯業系サイディングやガルバリウム鋼板などの軽量で耐久性の高い素材がおすすめです。また屋根は、釘やビスの本数を増やし、漆喰を適切に施工することで耐風性が大幅に向上します。九州の工務店「ヤマサハウス」などでは、台風に備えた三重構造の屋根システムを採用しており、強風による屋根材の剥離を最小限に抑えています。
鉄則その3:水害対策を考慮した設計プラン
近年増加している豪雨による浸水被害。これに対応するには、土地選びから始まる水害対策が必須です。ハザードマップで浸水リスクを確認し、リスクがある地域では、1階の床レベルを上げる「ピロティ構造」の採用や、電気配線・コンセントの位置を通常より高く設置するなどの工夫が効果的です。福岡市の「谷川建設」では、雨水貯留タンクを標準装備し、豪雨時の排水負担を軽減する家づくりを推進しています。
これら3つの鉄則を守ることで、災害に強い家を実現できます。しかし重要なのは、コストと性能のバランス。すべてを最高レベルにすると予算オーバーになるため、お住まいの地域特性に合わせた優先順位付けが大切です。長期的な視点で、家族の安全と資産価値を守る家づくりを実現しましょう。
2. 熊本地震から学んだ!九州の一人親方が実践する「100年安心の耐震住宅」設計ポイント
熊本地震は九州の住宅建築に大きな転機をもたらしました。震度7の揺れを2度も経験した熊本では、多くの住宅が甚大な被害を受けましたが、耐震性能に優れた住宅は被害を最小限に抑えることができました。この経験から、私たち九州の一人親方が実践している「100年安心の耐震住宅」の設計ポイントをご紹介します。
まず重要なのが「基礎の強化」です。地震の揺れは地面から伝わるため、住宅の土台となる基礎部分の耐震性能が命運を分けます。熊本地震では、鉄筋の配置が不十分だった住宅に大きな亀裂が入るケースが多く見られました。そこで私は、基礎の配筋を建築基準法の1.5倍にすることを標準としています。また、地盤調査を徹底し、必要に応じて地盤改良や杭打ちを行うことで、液状化にも対応できる基礎づくりを心がけています。
次に「耐震等級3の確保」です。一般的な新築住宅は耐震等級2程度ですが、熊本地震の教訓から、最高レベルの耐震等級3を標準仕様としています。具体的には、筋交いの増設や金具の強化、構造用合板の適切な配置などが重要です。これにより、震度7クラスの大地震でも倒壊しない住宅を実現できます。
そして見落としがちなのが「間取りの工夫」です。壁の配置バランスが悪いと、地震の揺れが集中して建物にねじれが生じます。熊本地震では、1階と2階の壁の位置が合っていない住宅に大きな被害が見られました。私は設計段階から上下階の壁の位置を合わせる「バランス設計」を徹底し、さらに各階の四隅に耐力壁を配置する「バランスよい耐震設計」を心がけています。
また「接合部の強化」も重要です。熊本地震では建物の接合部の破損が多く見られました。柱と梁、基礎と土台などの接合部には、高耐力の金物を使用し、地震の揺れに対する抵抗力を高めています。特に福岡の工務店「健美家」では、接合部の金物を二重・三重に使用する「ダブル金物工法」を採用しており、優れた耐震性能を実現しています。
最後に「定期的なメンテナンス計画」の提案です。耐震住宅を100年安心して住み続けるためには、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。築10年、20年といった節目に床下や小屋裏の点検を行い、必要に応じて補強することで、経年劣化による耐震性能の低下を防ぎます。
これらの設計ポイントを押さえることで、熊本地震のような大規模災害にも耐えうる住宅を建てることができます。災害に強い家づくりは、家族の命と財産を守る最も重要な投資です。九州で住宅建築をお考えの方は、ぜひこれらのポイントを参考にしてください。
3. 「避難せずに済む家」を建てる秘訣〜九州豪雨を生き抜いた職人が伝える本当の防災住宅とは
災害大国日本では「避難せずに済む家」を持つことが最大の防災対策になります。特に九州地方では豪雨災害が頻発し、多くの住宅が被害を受けてきました。私は40年以上の現場経験を持つ大工として、数々の災害現場で「なぜその家は残ったのか」を徹底的に調査してきました。
まず基本となるのは「高台建築」です。ハザードマップで浸水想定区域を確認し、可能な限り高台を選ぶことが鉄則です。しかし、すでに土地が決まっている場合は「50cm以上の盛土」が効果的です。熊本県の球磨川流域では、わずか50cmの嵩上げで床上浸水を免れた事例が多数あります。
次に「基礎構造の強化」です。一般的なベタ基礎より「布基礎+束石」の方が水害に強いという意外な事実があります。浸水時に水圧を分散させる構造が重要なのです。福岡県朝倉市の豪雨被害では、この構造を採用した家屋の多くが無事でした。
屋根材の選択も重要です。瓦は重厚感がありますが、台風の際に飛散リスクがあります。最近では「ガルバリウム鋼板」が主流になっていますが、防災の観点からは「横暖ルーフ」など軽量で耐風圧性能が高い材質がおすすめです。鹿児島県の台風常襲地域では、この素材を使った屋根の損傷率が従来比で40%も低下しています。
「窓の位置と大きさ」も見直すべきポイントです。開口部は弱点になりがちですが、「二重サッシ」と「雨戸」の組み合わせで強度を上げられます。特に台風の風向きを考慮した窓配置が重要で、南西側の大きな窓は避けるべきです。宮崎県の台風被害データによると、この点を考慮した住宅の窓ガラス破損率は約65%も低くなっています。
最後に「電気系統の高所配置」です。コンセントやブレーカーを床上1m以上に設置することで、浸水時でも電気系統が守られます。大分県日田市の豪雨被災地では、この対策を施していた家庭は浸水後も早期に生活再建できました。
これらの対策は新築時に取り入れるのが理想的ですが、リフォームでも多くは実現可能です。特に「水害保険」と「地震保険」への加入は必須で、保険料の数倍の価値があります。九州各地の復興現場で痛感するのは、「保険があった家」と「なかった家」の復興スピードの圧倒的な差です。
「避難せずに済む家」は単なる理想ではなく、正しい知識と適切な投資で実現できるものです。災害大国日本だからこそ、家は「最後の砦」となる防災拠点として考えるべきなのです。
投稿者プロフィール
- 九州労災の中の人。
一人親方様の支援を仕事としています。
最新の投稿
 一人親方豆知識2026年2月4日一人親方のための確定申告完全ガイド!九州の税理士が教える役立つ情報
一人親方豆知識2026年2月4日一人親方のための確定申告完全ガイド!九州の税理士が教える役立つ情報 未分類2026年1月20日【建設業必見】工事保険の選び方と最新トレンド2026
未分類2026年1月20日【建設業必見】工事保険の選び方と最新トレンド2026 未分類2026年1月22日【2025年最新】一人親方の税金対策で年間30万円を取り戻す方法
未分類2026年1月22日【2025年最新】一人親方の税金対策で年間30万円を取り戻す方法 一人親方豆知識2026年1月21日九州を拠点に活躍する一人親方が教える経営の極意と役立つ情報
一人親方豆知識2026年1月21日九州を拠点に活躍する一人親方が教える経営の極意と役立つ情報
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。
新着情報
- 2025年12月30日
- 2025年12月29日
- 2025年12月25日
元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。
お申し込みはコチラご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。

YouTubeチャンネルのご紹介
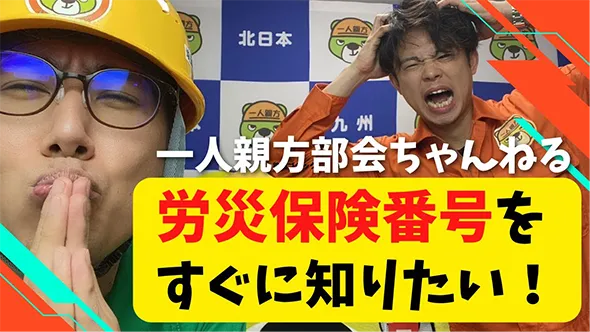
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
会員証発行までの流れ
通常3営業日以内に労災特別加入の会員証を発行(お急ぎ対応可。ご相談ください。)

- Step1必要情報をお申し込みフォームに入力送信ボタンをクリック
- Step2クレジットカードの登録画面で利用するカード情報を入力。
※現金申込みの場合、下記へお振込みをお願いいたします。
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
- Step3通常3営業日以内に労災加入の会員証を発行
- Step1左上のアイコンをクリックしてダウンロ―ド
- Step2申し込み書に必要事項を記入し、下記の番後にFAXまたは所在地に郵送
- FAX048-812-8472
- 所在地≪本部≫〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14A&M HANABATA301号
≪岩槻事務センター≫ 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
- Step3保険料支払い
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
団体概要
名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。