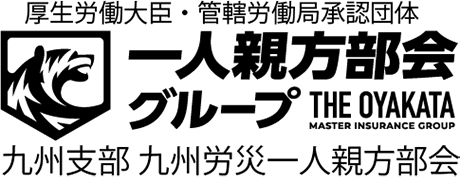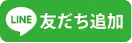労災保険
建設業許可と工事保険、開業の必須知識

建設業で新規開業をお考えの方、必要な許可や保険について悩んでいませんか?建設業界では、適切な許可取得と保険加入が事業の安定と成長に直結します。特に創業初期のトラブルを避けるためには、正しい知識を持っておくことが不可欠です。
本記事では、建設業許可の申請から工事保険の選び方まで、新規開業者が知っておくべき重要ポイントを徹底解説します。許可申請の煩雑な手続きや、事業リスクをカバーする最適な保険選びのコツをわかりやすくまとめました。
福岡を中心に九州地方で開業予定の方には特に役立つ地域密着型の情報もご紹介。行政書士に依頼すべきケースや、コスト削減しながらも十分な保障を確保する方法など、実践的なアドバイスが満載です。
これから建設業界に参入する方も、すでに開業したばかりの方も、この記事を参考にすることで許可申請のミスや保険選びの失敗を防ぎ、安心してビジネスをスタートできるでしょう。建設業での成功への第一歩は、正しい準備から始まります。
1. 【建設業界必見】新規開業で失敗しないための建設業許可と工事保険の完全ガイド
建設業界で新規開業を目指す方にとって、建設業許可と工事保険の知識は不可欠です。特に建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に法律で義務付けられており、無視できないポイントとなります。まず建設業許可取得には、専任技術者の配置や資本金額の要件など複数の条件を満たす必要があります。一般建設業許可では資本金300万円以上、専任技術者には実務経験10年以上または国家資格保有者が求められます。特定建設業許可ではさらに厳しい条件が課されるため、自社の事業規模を見極めた上で適切な許可区分を選択しましょう。
また工事保険については、第三者賠償責任保険、建設工事保険、労災上乗せ保険の3種類が基本となります。特に請負金額が大きい工事では発注者から保険加入を求められることが多く、万が一の事故や災害に備えて適切な保険に加入しておくことがリスク管理の要です。実際に現場で事故が発生し、保険未加入だったために数千万円の損害を自社負担した例も少なくありません。
建設業許可申請は自分で行うこともできますが、書類作成や要件確認の複雑さから行政書士などの専門家に依頼するケースが多いようです。費用は15万円から30万円程度が相場で、スムーズな開業のための投資と考えるべきでしょう。建設業許可と適切な工事保険の準備は、事業の安定と成長に直結する重要な経営判断です。計画的に準備を進め、堅実なスタートを切りましょう。
2. 建設業の新規開業者必読!許可申請のポイントと後悔しない工事保険の選び方
建設業で新規開業を考えている方にとって、建設業許可の取得と適切な工事保険の選択は事業の基盤となる重要事項です。実際、許可申請の不備や保険選びの失敗が原因で、開業後にトラブルを抱える事業者は少なくありません。ここでは、許可申請の核心ポイントと工事保険選択の実践的知識をご紹介します。
まず建設業許可申請では、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の確保が最重要です。経営業務の管理責任者には、建設業での経営経験が5年以上ある方、または同等の能力を持つ方が必要です。一方、専任技術者には国家資格や実務経験などの条件があります。この人材要件が最も多くの申請者が躓くポイントとなっています。
資金面では、500万円以上の自己資本と、流動比率75%以上などの財務要件も満たさなければなりません。これらの要件を確実に満たすため、行政書士など専門家への相談が効果的です。例えば東京都内の行政書士事務所では、許可申請のサポート料金が15〜30万円程度で提供されており、不備のないスムーズな申請をサポートしています。
次に工事保険選びですが、基本となるのは「請負業者賠償責任保険」です。これは工事中の事故で第三者に与えた損害をカバーする保険で、対人・対物賠償を含みます。しかし、これだけでは不十分なケースが多いのが現実です。
実際、東北地方の建設会社Aでは、下請け業者の作業ミスで隣接建物に損害を与えた際、請負業者賠償責任保険だけでは保証範囲外となり、多額の自己負担が発生したケースがありました。このような事態を防ぐため、「建設工事保険」や「組立保険」を追加することで、工事対象物自体の損害もカバーできます。
さらに請負金額が大きい場合や、複雑な工事を行う場合は「工事履行保証保険」も検討すべきです。これは工事が予定通り完了できない場合の補償を提供します。また、労災上乗せ保険である「法定外労災保険」も従業員の安全と企業防衛の観点から重要です。
保険選びでは大手保険代理店だけでなく、建設業専門の保険ブローカーへの相談が有効です。例えば、建設業に特化した保険代理店「日本建設業保険サービス」では、業種や工事内容に応じた最適な保険プランを提案しています。
建設業許可と工事保険は、単なる法的義務や形式的な備えではなく、事業継続の基盤となる重要な要素です。開業前に十分な時間をかけて準備し、専門家のアドバイスを受けながら最適な選択をすることで、将来の大きなリスクを回避できます。
3. 建設業許可取得から工事保険加入まで – 新規開業で絶対に知っておくべき重要ステップ
建設業を新規開業する際、建設業許可の取得と適切な工事保険への加入は避けて通れない重要なステップです。これらの手続きを適切に行わないと、大型工事の受注機会を逃すだけでなく、事故発生時に多額の損害賠償責任を負うリスクも高まります。
【建設業許可取得の基本ステップ】
建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。取得手順は以下の通りです。
1. 許可要件の確認:経営業務管理責任者の設置、専任技術者の配置、財産的基礎(自己資本500万円以上など)を満たす必要があります。
2. 申請書類の準備:申請書、工事経歴書、財務諸表、定款などの書類を準備します。
3. 管轄行政庁への申請:都道府県知事または国土交通大臣に申請します。東京都の場合、都庁の建設業課に申請書を提出します。
4. 審査と許可取得:書類審査と場合によっては実地調査を経て、約1〜2ヶ月で許可が下ります。
【必須加入の工事保険とその選び方】
工事中の事故や品質トラブルに備えるため、以下の保険への加入を検討すべきです。
1. 請負業者賠償責任保険:工事中に第三者へ与えた損害を補償します。東京海上日動や三井住友海上などが提供する商品が一般的です。
2. 建設工事保険:工事中の災害による工事目的物の損害を補償します。
3. 労災上乗せ保険:従業員の労災事故に対する上乗せ補償となります。
4. 生産物賠償責任保険(PL保険):引き渡し後の建物の欠陥による事故を補償します。
【許可取得と保険加入の実務上のポイント】
実務では、建設業許可申請は行政書士に依頼するケースが多く、費用は15〜30万円程度です。また、保険は複数の保険会社から見積りを取り、補償内容と保険料のバランスを比較検討することが重要です。
大手ゼネコンとの取引では、一定の補償金額を持つ保険への加入が取引条件となることも多いため、業界標準を把握しておくことも必要です。また、建設業許可は5年ごとの更新が必要であり、更新漏れによる営業停止を防ぐためのスケジュール管理も重要なポイントです。
適切な許可取得と保険加入は、建設業の安定経営の基盤となります。初期費用はかかりますが、事業の信頼性向上と将来的なリスク軽減のための必須投資と考えるべきでしょう。
投稿者プロフィール
- 九州労災の中の人。
一人親方様の支援を仕事としています。
最新の投稿
 一人親方豆知識2026年1月14日九州の気候に合わせた建築術!一人親方が伝える地域特有の役立つノウハウ
一人親方豆知識2026年1月14日九州の気候に合わせた建築術!一人親方が伝える地域特有の役立つノウハウ 未分類2026年1月15日青色申告のメリット・デメリット|一人親方の税金戦略を解説
未分類2026年1月15日青色申告のメリット・デメリット|一人親方の税金戦略を解説 一人親方豆知識2026年1月16日九州の一人親方必見!仕事を10倍効率化する現場の裏ワザと豆知識集
一人親方豆知識2026年1月16日九州の一人親方必見!仕事を10倍効率化する現場の裏ワザと豆知識集 一人親方豆知識2026年1月12日独立10年の九州一人親方が語る!失敗から学んだ成功への道と役立つ情報
一人親方豆知識2026年1月12日独立10年の九州一人親方が語る!失敗から学んだ成功への道と役立つ情報
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。
新着情報
- 2025年12月30日
- 2025年12月29日
- 2025年12月25日
元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。
お申し込みはコチラご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。

YouTubeチャンネルのご紹介
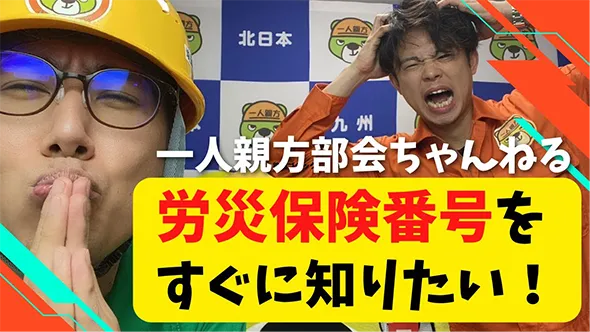
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
会員証発行までの流れ
通常3営業日以内に労災特別加入の会員証を発行(お急ぎ対応可。ご相談ください。)

- Step1必要情報をお申し込みフォームに入力送信ボタンをクリック
- Step2クレジットカードの登録画面で利用するカード情報を入力。
※現金申込みの場合、下記へお振込みをお願いいたします。
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
- Step3通常3営業日以内に労災加入の会員証を発行
- Step1左上のアイコンをクリックしてダウンロ―ド
- Step2申し込み書に必要事項を記入し、下記の番後にFAXまたは所在地に郵送
- FAX048-812-8472
- 所在地≪本部≫〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14A&M HANABATA301号
≪岩槻事務センター≫ 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
- Step3保険料支払い
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
団体概要
名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。