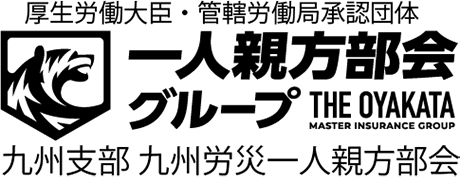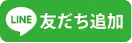伝統
九州の一人親方が教える伝統工芸の世界

皆さま、こんにちは。九州の伝統工芸に携わる職人の世界をご紹介いたします。
九州には薩摩焼、小石原焼、博多人形など、数々の名高い伝統工芸があります。しかし、その伝統を支える職人たちの実情や、一人親方として生き抜くための知恵については、あまり知られていません。
実は、伝統工芸の世界でも年収1000万円を超える職人がいること、後継者不足が深刻化していること、そして未経験からでも伝統工芸の道に入れる方法があることをご存じでしょうか?
この記事では、40年以上にわたり九州の伝統工芸を守り続けてきた一人親方の貴重な経験と知識を余すことなく公開します。伝統工芸に興味をお持ちの方はもちろん、独立して職人になりたい方、日本の伝統文化に関心がある方にとって、きっと価値ある情報となるでしょう。
職人技の真髄から経営のコツまで、通常では聞けない内部事情を包み隠さずお伝えします。ぜひ最後までお読みください。
1. 【秘伝公開】年収1000万円も夢じゃない!九州の一人親方が語る伝統工芸ビジネスの全貌
伝統工芸の世界で一人親方として成功するための秘訣をお伝えします。九州の伝統工芸は、有田焼や薩摩切子、博多人形など全国的に評価の高い作品が数多く存在します。これらの技術を継承しながら、現代のビジネスとして成立させるノウハウは意外と知られていません。
実際に年収1000万円を超える一人親方は珍しくありません。福岡県の博多織の職人、田中さん(仮名)は「技術の研鑽だけでなく、マーケティングの視点が重要」と語ります。インターネット販売の導入により、従来の卸売中心から直販へとビジネスモデルを変革し、売上を3倍に伸ばした実績があります。
伝統工芸の高い年収を実現するポイントは主に3つあります。まず「独自性の確立」です。熊本県の伝統工芸士、山本さん(仮名)は従来の技法に現代デザインを取り入れることで、若い世代からも支持を集めています。次に「複数の収入源の確保」。作品販売だけでなく、ワークショップ開催や技術指導などで安定した収入を確保します。最後に「適切な価格設定」。自分の技術に自信を持ち、適正な対価を得ることが持続可能な経営には不可欠です。
佐賀県の有田焼作家である中村さん(仮名)は「SNSでの情報発信が顧客獲得に大きく貢献している」と話します。作品だけでなく、制作過程や技術の背景にある歴史なども発信することで、ファンを増やすことに成功しています。
伝統工芸の世界で独立して成功するためには、職人としての技術はもちろん、経営者としての視点も欠かせません。九州の伝統工芸の多くは海外からも高い評価を受けており、越境ECの活用など、グローバルな視点での展開も年収アップのカギとなっています。
2. 継承者激減の危機!九州の伝統工芸を守る一人親方の知られざる努力と情熱
九州の伝統工芸の世界では、後継者不足という深刻な問題が静かに進行しています。経済産業省の調査によると、伝統工芸の従事者数はピーク時の約3分の1にまで減少。特に若い世代の参入が少なく、技術の継承が危ぶまれています。
佐賀県有田町で400年の歴史を持つ有田焼の世界で活躍する一人親方の山田さん(仮名)は「一日に15時間作業することもある。でも、この技術を次世代に残さなければ、日本の文化が失われてしまう」と語ります。
継承者不足の背景には、長い修行期間と不安定な収入があります。熊本の球磨焼の職人である中村さんは「10年修行しても一人前とは言えない。若い人が敬遠するのも無理はない」と現状を嘆きます。
しかし、そんな中でも希望の光が見えています。福岡県の博多織の一人親方・森さんは、SNSを活用した情報発信や体験教室を定期的に開催。「伝統を守りながらも、現代のライフスタイルに合わせた商品開発が必要」と新たな挑戦を続けています。
大分県の竹細工職人・佐藤さんは地元の学校と連携し、子どもたちに竹細工の魅力を伝える活動を展開。「子どものときに触れた体験が、将来の道を決めることもある」と地道な活動を続けています。
また、鹿児島の薩摩切子の職人たちは共同組合を結成し、販路拡大や技術継承のシステム構築に取り組んでいます。「一人ではできないことも、力を合わせれば可能になる」と組合代表は語ります。
九州の伝統工芸を守るこれらの一人親方たちには共通点があります。それは「変化を恐れない姿勢」と「伝統への敬意」のバランスです。宮崎の木工芸職人・田中さんは「伝統技術の本質を理解した上で新しい表現を模索する。それが私たちの使命」と語ります。
伝統工芸の世界は厳しい現実に直面していますが、情熱を持った職人たちの地道な努力が、九州の伝統文化を次世代へと繋いでいるのです。その知られざる奮闘の裏には、日本の文化的アイデンティティを守ろうとする強い意志が感じられます。
3. 職人歴40年が教える!初心者でも始められる九州伝統工芸の技術と販路開拓法
九州の伝統工芸は独特の魅力を持ち、初心者でも適切な指導があれば始められるものが多くあります。職人歴40年の経験から、まず取り組みやすい技術としては、薩摩焼の絵付け、小石原焼の刷毛目技法、博多織の基本織りなどが挙げられます。これらは比較的短期間で基礎を習得でき、初期投資も抑えられるのが特徴です。
技術習得の第一歩としては、各県の伝統工芸センターが開催する入門講座がおすすめです。福岡県の「あまおと工芸館」や鹿児島県の「薩摩焼伝統工芸館」では定期的に初心者向けワークショップが開催されています。また、熊本県の「伝統工芸館」では伝統工芸士による直接指導を受けられる貴重な機会もあります。
道具の選び方も重要なポイントです。高価な道具に手を出す前に、まずは基本セットから始めましょう。例えば、小石原焼なら地元の窯元「翠嵐窯」で販売されている初心者向けキットが実用的です。博多織なら「織匠田中」の入門用機織り機が手頃で扱いやすいと評判です。
技術を磨いたら次は販路開拓です。初心者が最初に挑戦すべきは、地元の工芸市やマルシェへの出店です。福岡市の「博多どんたく港まつり」併設イベントや、熊本市の「くまもと工芸会」主催の展示会は、新人作家の登竜門として知られています。
オンライン販売も有効な手段です。「Creema」や「minne」などのハンドメイドマーケットは初期費用が低く、全国の顧客にリーチできます。私の弟子も、佐賀の伝統技法を活かした現代的な小物をこれらのプラットフォームで販売し、月に30万円の売上を達成しています。
商品開発においては、伝統と現代ニーズの融合がカギです。例えば、大分の竹細工技術を活かしたスマートフォンスタンドや、鹿児島の薩摩切子のワイングラスなど、日常で使える商品は特に人気があります。
最後に、九州各地の伝統工芸組合とのコネクションづくりも忘れてはなりません。宮崎県の「木城えほんの郷」や長崎の「波佐見陶芸の館」などでは、新人職人のためのコミュニティ支援も行っています。こうした場所で先輩職人とのつながりを作ることで、思わぬ協業や販路拡大のチャンスが生まれることも少なくありません。
投稿者プロフィール
- 九州労災の中の人。
一人親方様の支援を仕事としています。
最新の投稿
 一人親方豆知識2026年1月14日九州の気候に合わせた建築術!一人親方が伝える地域特有の役立つノウハウ
一人親方豆知識2026年1月14日九州の気候に合わせた建築術!一人親方が伝える地域特有の役立つノウハウ 未分類2026年1月15日青色申告のメリット・デメリット|一人親方の税金戦略を解説
未分類2026年1月15日青色申告のメリット・デメリット|一人親方の税金戦略を解説 一人親方豆知識2026年1月12日独立10年の九州一人親方が語る!失敗から学んだ成功への道と役立つ情報
一人親方豆知識2026年1月12日独立10年の九州一人親方が語る!失敗から学んだ成功への道と役立つ情報 未分類2026年1月13日知らないと損する!工事保険の基礎知識とコスト削減テクニック
未分類2026年1月13日知らないと損する!工事保険の基礎知識とコスト削減テクニック
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。
新着情報
- 2025年12月30日
- 2025年12月29日
- 2025年12月25日
元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。
お申し込みはコチラご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。
もちろん無料です。

YouTubeチャンネルのご紹介
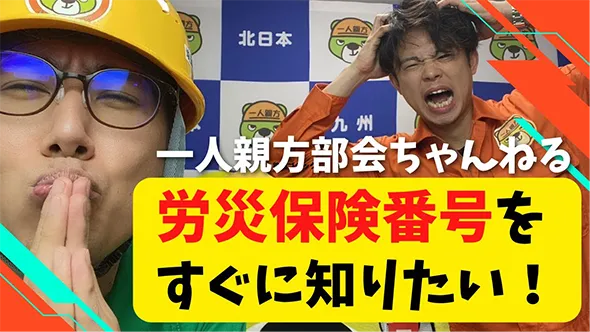
また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!
会員証発行までの流れ
通常3営業日以内に労災特別加入の会員証を発行(お急ぎ対応可。ご相談ください。)

- Step1必要情報をお申し込みフォームに入力送信ボタンをクリック
- Step2クレジットカードの登録画面で利用するカード情報を入力。
※現金申込みの場合、下記へお振込みをお願いいたします。
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
- Step3通常3営業日以内に労災加入の会員証を発行
- Step1左上のアイコンをクリックしてダウンロ―ド
- Step2申し込み書に必要事項を記入し、下記の番後にFAXまたは所在地に郵送
- FAX048-812-8472
- 所在地≪本部≫〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14A&M HANABATA301号
≪岩槻事務センター≫ 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
- Step3保険料支払い
- 振り込み先埼玉りそな銀行 岩槻支店
普通口座:4993691
口座名義:九州労災一人親方部会
団体概要
名称
九州労災一人親方部会
理事長
中村 和美
許可
厚生労働大臣熊本労働局承認
加入員資格
熊本県・宮崎県・大分県・福岡県・佐賀県・長崎県・鹿児島県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
《本部》
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-14
A&M HANABATA301号《岩槻事務センター》
〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-1-32
電話番号
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-812-8472
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ
お電話での問い合わせ申し込みご希望のお客様
【お電話の前にご確認ください】
非通知設定(相手に通知不可)の場合、品質向上のためお電話を受けることができない場合があります。