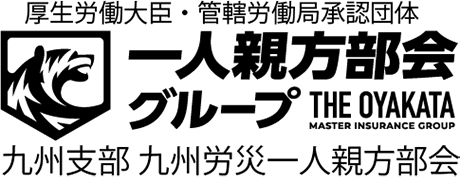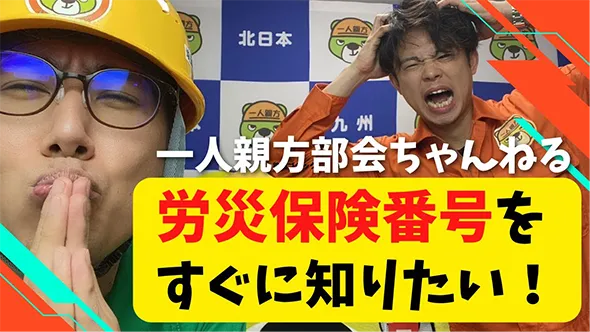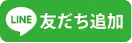九州の建設業界で一人親方が20年間生き残るための人脈術と仕事選び
建設業界で一人親方として長く働くには技術だけでは不十分。九州では「人とのつながり」が仕事の質と量を左右します。福岡・熊本・鹿児島など各地での経験をもとに、現場で役立つ実践的なコツをまとめました。
挨拶と信頼がすべての始まり
九州の現場は「顔の見える関係」が基本です。現場に入る際は元請けや職人に明るく挨拶し、今日の作業を一言伝えるだけで印象が変わります。朝の挨拶を大切にするだけで、調整や声がかかりやすくなります。
飲みニケーションは情報源でもある
仕事終わりの一杯で次の現場の話が決まることもあります。鹿児島や長崎の居酒屋で交わす会話は貴重なネットワークです。ただし愚痴や他社批判は厳禁。信用を失うと取り戻すのは困難です。
地元密着で情報を先取りする
地元の工務店やホームセンターは発注情報のハブです。定期的に顔を出して店員と会話することで、思わぬ仕事の話が入ることがあります。顔を覚えてもらう努力が、安定した仕事につながります。
断るべき仕事・逃げるべき現場の見分け方
大手ゼネコンや継続的に依頼をくれる地元の有力企業は基本的に受けるべき案件です。逆に支払いサイトが極端に長い、保護具や安全管理が不十分、初回から過度な値引きを要求する元請けは要注意。人間関係のトラブルが絶えない現場も避けるべきです。
ギブ&テイクで築く長期的な信頼
先にギブする姿勢(道具の貸し出し、差し入れ、手伝い)は信頼を生みます。反対に助けが必要なときは遠慮せずに「声をかけてほしい」と伝えること。LINEやSNSで施工写真や解決策を共有すると「頼れる親方」として評判が広がります。
日々の積み重ねが将来の仕事をつくる
熊本地震の復旧工事では、日頃の信頼関係が仕事につながった例もあります。技術は磨けますが、人間関係は育てるもの。目先の損得にとらわれず、長期的な信頼構築を心がけることが、安定した仕事確保の近道です。